業務の棚卸しとは 4ステップに集約したやり方を解説
業務の棚卸しは社内の業務を洗い出して、整理していく取り組みです。その目的は業務改善や人員配置の最適化、属人化防止など多岐にわたります。
働き方改革の推進やリモートワークの普及といった働き方の多様化を受けて、業務の棚卸しの必要性が高まる一方、棚卸しから課題解決にまで結び付けられている企業はあまり多くありません。
今回は、業務の棚卸しが注目される背景や目的・メリットなどを踏まえたうえで、棚卸しのやり方を4つステップに集約して解説していきます。
業務の棚卸しとは
業務の棚卸しとは、社内のあらゆる業務について、その内容や方法などを整理していく取り組みです。
もともと棚卸しは「決算などの際、物品の現在の総数を調査・確認すること」という意味で、資産評価の意味合いが含まれる場合もあります。ここから転じて、社内で行われている業務について、内容や方法、作業時間、コストなどを調査・確認することを「業務の棚卸し」と呼ぶようになりました。

業務の棚卸しが注目される背景
業務の棚卸しが注目される背景として、主に「働き方の多様化への対応」と「DXの推進」が挙げられます。
働き方の多様化への対応
業務の棚卸しが注目される最大の背景として、働き方の多様化への対応が挙げられます。
以前より働き方改革によってフレックスタイム制度の導入などが着実に進んでいましたが、コロナ禍をきっかけにリモートワークが急速に普及し、就業のかたちはさらに大きく変化しました。そして、こうした就業環境の変化によって生じているのが、チームメンバーが直接コミュニケーションを取る機会が減るという問題です。
これに対応するため、各従業員の業務の状況などを把握するための業務の棚卸しが求められているわけです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
業務の棚卸しへの関心が高まるのは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進も深く関係しています。生成AIやloT技術を活用することで、新たな方法論の創出や劇的な業務短縮が実現可能となるからです。
とはいえ、なんでもかんでも最新技術を活用すればいいというわけではなく、業務との相性やコストなどを踏まえて導入を判断する必要があります。そこで必要となるのが、業務の棚卸しというわけです。

業務の棚卸しの目的・メリット
業務の棚卸しを行う目的および棚卸しによって得られるメリットを解説していきます。
業務改善・生産性の向上
業務の棚卸しの主要な目的は、業務改善や生産性の向上です。ムダが生じている工程や仕事量の分担、ムラの多い業務などを洗い出すことで、業務改善・生産性向上の手がかりとなります。ひいては、働き方改革のための時短推進にもつながるでしょう。
実際、社員それぞれが抱えている業務の難易度や量などは、意外と同じチームのなかですら正確に掴めていないことがあります。毎日残業をしていて作業が遅いと思われていた人が、実は他の人では処理できないような難しい案件を引き受けていた、といった話は珍しくありません。そのため、棚卸しを通じて社内の業務を可視化することが重要になるのです。
なお、業務のムリ・ムダ・ムラについては「ムリ・ムダ・ムラとは 発生の原因や「7つのムダ」について解説」でも詳しく解説しています。
社員間の共通認識
業務の棚卸しは、業務の内容について、社員間で共通認識を持たせる効果があります。
例えば社内の掃除について、社員Aは「自分のデスク周りだけで良い」と捉えているのに対し、社員Bは「オフィスの共用の廊下まで掃除をする」と捉えていたとします。これは指示に対する共通認識がなく、社員がバラバラに行動するリスクがあるということです。
掃除であれば大した問題ではありませんが、「資料を作成して」と指示を出し、社員によって異なる資料が作成されるようでは業務が破綻します。こうした業務の定義に対する認識のズレは大なり小なり組織内に散在しているため、業務の棚卸しによって「掃除は○○から△△まで」といった具合に共通認識を作る必要があるのです。
人員配置の最適化
業務の棚卸しは、人員配置の最適化にも役立つ取り組みです。棚卸しによってリソース不足の事業や業務過多となっている人員を明らかにすることは、人員の適切な配置に欠かせない情報となります。
また業務の棚卸しは、社員それぞれの適性に合った業務の割り振りにもつながります。業務にかかる時間やクオリティを可視化していくなかで、必要以上に時間・手間がかかっている部分があれば、その業務を得意とする別の人員に割り振ることも可能となります。
なお、人員配置については「人員配置とは 最適化のステップと考え方」でも詳しく解説しています。
業務の属人化の防止
業務の棚卸しは、業務の属人化の防止を目的に実施されることもあります。
製造業のマニュアルのように手順が明文化されている業務がある一方、中間管理職が陰ながら処理するような雑事は、なかなか周囲からは認識されません。こうした役割は担当者が不在になると再現が難しく、最悪の場合、担当者が離職した後に「なぜか業務が滞るようになってしまった」と、業務が属人化していたことにすら気づかないこともあります。
また、こうした表に出ていない業務を棚卸しによって可視化することは、人材の適切な評価にもつながってきます。

4ステップでわかる業務の棚卸しのやり方
業務の棚卸しの進め方を4ステップに集約して解説していきます。
棚卸しの対象(範囲)を決める
業務の棚卸しは、組織内のあらゆる業務が対象となります。そのため、対象をある程度絞らないと終わりのない取り組みとなってしまうので、「事業ごと」「部署ごと」「ハイリスクな業務」といった具合に棚卸しの範囲を明確にしておく必要があります。
また、業務の棚卸しは社員にも少なからず負担をかけることになるため、閑散期に実施することも大切です。
業務棚卸表をもとにした業務の書き出し
対象(範囲)を決めたら、その業務に携わる社員全員に業務の書き出しをしてもらいます。このとき、それぞれが自由に記載すると文章力や性格などによって内容に差が出てしまうため、あらかじめ記載内容のフォーマット(業務棚卸表)を用意しておきましょう。
業務棚卸表は基本的に「大分類」を頂点としたピラミッド構造で、「中分類」「小分類」と細分化していきます。
〈例〉
「大分類:営業活動」「中分類:商談の事前準備」「小分類:市場調査」「小分類:資料作成」
とくに小分類は「書き出すほどの業務と思っていない」「失念している」といった理由から、必ず漏れが出てきます。担当者は業務棚卸表を整理する際、部署ごとに内容を比較して、疑問点があれば再確認を行うようにしましょう。
また、「承認フロー」「発生するコスト」など、業務遂行にあたって必要となる情報を補足しておくと、属人化の防止につながります。職種や業務内容によっても必要となる情報は異なるので、適宜カスタマイズしていくことも大切です。
業務量調査
業務棚卸表をベースとして、業務量調査を行います。各業務がどれくらいの頻度で発生し、どの程度の作業時間が必要となっているかをまとめた上で、年間業務量を計算します。
作業時間の平均時間を算出し、各担当者ごとに比較することで、業務に対する適性や生産性を探る手がかりとなります。ただし、作業時間は業務の質やクライアントの満足度などに比例している可能性もあるため、作業時間の長短だけで評価を行うべきではありません。
定期的な情報の更新
業務の棚卸しは、一度きりの取り組みではありません。近年は技術革新によって抜本的に業務フローが変更されることも少なくないため、定期的に棚卸しを実施していく必要があります。人員の入れ替わりによっても変化は生じるため、まめな情報の更新を心がけましょう。

業務の棚卸しで活かせるフレームワーク
業務の棚卸しといっても「どのような方法で行うべきなのだろう」「何に気をつければいいかわからない」という方も多いことでしょう。ここでは、業務の棚卸しで活かせるフレームワークをご紹介します。
BPMN
BPMN(Business Process Model and Notation)とは、業務フローを作成するためのフレームワークであり、国際標準(ISO19510)によって定められていることから誰が見ても同じ意味として伝わるという特徴があります。「業務棚卸表をもとにした業務の書き出し」で解説したフォーマットとして活用するのもよいでしょう。
業務フローを作成する人によって表現方法が異なっては、社内全体での共通認識が得られず、せっかくの業務の棚卸しが意味のないものになってしまいます。そこで役立つのがBPMNによる表現で、これを用いることで他部署とのあいだでも共通認識が得られるフローチャートとなるわけです。
ECRS
ECRS(イクルス)は「Eliminate(排除)」「Combine(結合)」「Rearrange(再配置・入れ替え)」「Simplify(簡素化)」の頭文字で構成されており、業務改善の指針を定める際に活用されるフレームワークです。「業務改善の4原則」とも呼ばれ、主に業務の棚卸しの「業務改善・生産性の向上」に活かせる手法です。
ECRSを活用することで業務改善の方向性が定まり、以下のように具体的な取り組みが検討しやすくなります。
・排除:不要なタスクや業務を取り除く
・結合:類似している業務を一本化する
・再配置:担当者の再配置や作業工程の組み換え
・簡素化:マニュアルによる業務の標準化やExcelのマクロ処理化
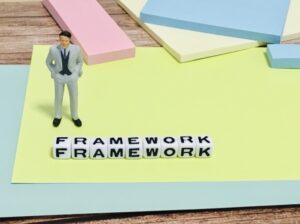
業務の棚卸しを行う際の注意点
業務の棚卸しを行う際、あらかじめ注意しておくべきポイントをお伝えします。
独断で業務の必要性を判断しない
業務の棚卸しの際、上層部などの独断で業務の必要性を判断してしまうと、生産性を落とす結果になりかねません。一見すると無駄に感じる業務も、現場を円滑に回す秘訣になっているというのは、よくある話です。
「意図が不明瞭だから」と安易に改善指示を出す前に、必ず現場を含めて業務の必要性について議論の場を設けましょう。
人的要因にも目を向ける
業務のなかで不自然に工数・時間がかかっているものがあった場合、人間関係・コミュニケーションといった人的要因にも目を向けてみましょう。人の働きは感情によって大きく左右され、プレッシャーやストレスなどによっても生産性は変化します。場合によっては「上司が過度なプレッシャーを与えていないか」など、人的な問題点についても調査する必要があります。
無理に社内での解決を目指さない
社内で負担となっている業務や、繁閑によってムラが生じている業務がある場合は、無理に社内で解決しようとせずにアウトソーシングも検討しましょう。とくに社内のリソースが不足している場合、アウトソーシングを活用するほうが結果的にコスト減につながることもあります。
近年では副業の推進やクラウドソーシングの普及もあり、外注の選択肢も広がっています。コストパフォーマンスを考えて選択肢を広げておくことで、業務の棚卸しの効果も向上するでしょう。

業務の棚卸しに求められる数字力
業務の棚卸しでは、単に社内に存在する業務を可視化していくだけでなく、その効率性や生産性なども合わせて把握し、具体的な改善アクションへと結び付けなければいけません。
例えば、「棚卸しの結果、◯◯部のAさんとBさんの年間業務量には、△△時間の差があることがわかりました」と報告するだけでは、なんの改善にも結びつきません。「なぜ、AさんとBさんの年間業務量の差が生じているのか」「改善のためには、どんな施策が必要なのか」といった建設的な情報・提案へと昇華しないと、業務の棚卸しの成果は得られないのです。
では、データの相関関係などからポイントを見つけだし、具体的な施策を導き出すために何が必要なのかというと、ずばり「数字力」です。
弊社オルデナール・コンサルティングがご提供する「ビジネス数学研修」は、ビジネスシーンで必要となる「数字力」を鍛えるための研修であり、数字・データを根拠としたアクションプランの立て方を実践形式で学んでいきます。
研修は受講者のレベルに合わせて「入門編」から「実践編」の4段階で学べるので、数字に対する苦手意識を持つ方でも安心してステップアップしていくことができます。 「業務の棚卸しをしたものの、成果に結びつかない」「問題解決のためのデータの見方・扱い方を学びたい」といった課題にお悩みでしたら、ぜひ弊社の研修プログラムをご活用ください。
オルデナール・コンサルティング合同会社は「ビジネスで活用する数字力向上」に特化した人材教育サービスをご提供します
続きを読む