オーバーコンプライアンスとは 日本企業を弱らせる「3つの過剰」を解説
オーバーコンプライアンスは「過剰な法令遵守、過剰規則」といった意味があり、下の記事のように「3つの過剰」のひとつとして、日本の国際競争力の低下の原因と指摘されています。
「日本企業にありがちな「3つの過剰」の大きな弊害」(2022年3月10日「東洋経済ONLINE」)
会社員として働くなかで、厳しすぎるルールに苛立ちを覚えた経験がある人も多いと思います。私も会社員時代、新規事業開発に携わっていたときにオーバーコンプライアンスで仕事が進まなかった経験があります。
当時、数万円のトライアル費用が必要となったため会社に申請したのですが、1時間以上の打ち合わせを何回も繰り返すことになり、決裁を得るまで長い時間と労力がかかりました。「費用は自分で払うので、勝手にやらせて下さい」と何度言いたくなったかわかりません。
今回は、そんなオーバーコンプライアンスや「3つの過剰」について解説していきます。
オーバーコンプライアンスとは
オーバーコンプライアンスとは「過剰な法令遵守、統制過剰、過剰規則」といった意味を持つ言葉です。
オーバーコンプライアンスという言葉が広まったのは、一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏が日本の国際競争力の低下の原因として指摘した「3つの過剰」からです。
・オーバーアナリシス(過剰分析)
・オーバープランニング(過剰計画)
・オーバーコンプライアンス(過剰規則)
分析ばかりに時間を割き、計画を細部まで何度も練り直し、行きすぎた規則で行動を縛る……こうした過剰な管理が、生産性の低下やイノベーションの阻害につながっているという指摘です。
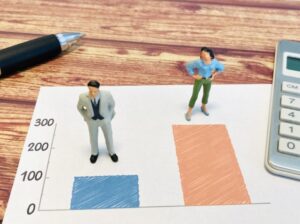
「3つの過剰」が生まれる背景
「3つの過剰」が生まれる背景として、合理主義的経営手法の広まりが挙げられます。
「失われた30年」のなかで、多くの日本企業が再建を図るために欧米式の合理主義的経営手法を取り入れました。これによって売上や利益を始めとした業績、株価、KPIなど、経営において「数字」が重んじられるようになったわけです。
こうした「数字」を達成するためには、綿密な経営計画が欠かせません。そして綿密な計画を作成するためには、成功・失敗の分析とイレギュラーが起きないような統制が求められます。
これらの取り組み自体は悪いことではありませんが、日本人の生真面目な性格も相まって、計画・分析・規則が行きすぎてしまい「3つの過剰」に陥ってしまうのです。

オーバーコンプライアンスの悪影響・デメリット
組織がオーバーコンプライアンスに陥ることで「スピード感の低下」「現場の疲弊」「社員が指示待ち型になる」といった悪影響・デメリットが生じます。それぞれ解説していきましょう。
スピード感の低下
オーバーコンプライアンスの最たる悪影響として、組織のスピード感の低下が挙げられます。
「問題を起こしてはいけない」「リスクをゼロにしなければならない」といったルールのなかでは気軽に行動を起こせず、選択肢も制限されます。これでスピード感のある組織運営ができるわけがありません。
現場の疲弊
オーバーコンプライアンスは現場の疲弊を招きます。例えば、過剰な法令遵守の意識で意思決定が遅れてスケジュールが圧迫されると、その遅れた時間は現場でカバーすることになります。社内の事情で計画に遅れが生じたとしても、納期は待ってくれないからです。
また、ルールを守るために細心の注意を払うことでも、やはり神経はすり減っていきます。このように、オーバーコンプライアンスはいたずらに現場を疲弊させ、じりじりと組織全体の体力を低下させていくのです。
社員が指示待ち型になる
オーバーコンプライアンスが生じている組織では、社員が指示待ち型になります。決められた計画や厳しいルールのなかでしか動けない環境では、社員は指示されたことしかしなくなります。
さらにこうした環境では「お客様のため」「社会のため」といった目標よりも、ルールを守ることや計画を遂行することが優先されるようになり、イノベーションのチャンスを失うことになります。

加点方式でビジネスを進めることが人事育成につながる
企業がオーバーコンプライアンスを始めとした「3つの過剰」を求める理由は様々ありますが、私は減点方式の組織体制に問題があると考えています。
減点方式が染みついている組織では、失敗が許されません。「失敗=自分の地位が揺らぐ」ので、上の立場の人ほど部下に対して完璧を求めます。これが数字による行き過ぎた管理を招いてしまうわけです。
弊社の「ビジネス数学研修」の受講者でも「数字は正しい」という認識を持つ方は多く、課題に対して100点の正解を探そうとする方は少なくありません。しかし、ビジネスに100点満点の正解などありません。どれだけ時間を掛けて分析しても、明日の売上を正確に予測することはできません。未来のことは誰にもわからないからです。
そのため、弊社の研修で実施する多くの演習には「答え」がありません。複数の選択肢から最も良い考えを選び、他者に対して「なぜそれを選んだのか」をわかりやすく伝えることが研修のポイントとなっております。 「ビジネスシーンに100%の正解はない」ことを前提として、減点方式ではなく加点方式でビジネスを進めることが人事育成につながると信じています。
オルデナール・コンサルティング合同会社は「ビジネスで活用する数字力向上」に特化した人材教育サービスをご提供します
続きを読む